若草幼稚園では「安穏」(安心して、穏やかに)を一番大切な価値観として保育にあたっています。
日本の子どもたちはいつも、必要以上に興奮状態にあるように感じています。
元気な子どもがいい、元気な声がいい、大きな声で挨拶しましょう、子どもは風の子など、子どものテンションを上げようとする場面が多くみられます。子どももそうでないといけないと思ってしまい、元気な子どももも、テンションの高い子どもを演じているように見えます。大人も子どもは大きな声で話すもので、穏やかにそこにいることはできないと思っているようです。
子どもは安心できると穏やかになります。ところが、ここ何十年かの子どもたちを取り巻く環境は、子どもたちに緊張を強いて安心できる状況ではないように感じます。
子どもが安心できるのは、自分が自分のままで、あるがままにその場所にいられるかどうかです。園が子どもを自分のままでいられる場所かどうかを考える必要があると思います。
子どもはいつも周りにいる大人の顔色を見ながら生きています。まず、そのことをしっかりわかってあげないといけません。子どもは小さいのです。子どもの身長は大人の半分くらいいかありません。ということは、もし大人が子どもなら、大人は3m近い大巨人です。それは怖いです。そのことを理解して、子どもに、顔色を見なくても大丈夫だよということをどう伝えていくかということです。
本園は自分のすることは自分が決めることを大切にしている幼稚園です。子どもたちは毎日ほとんどの時間を自分のしたい遊びを見つけて過ごしています。弁当の時間と、帰る前の30分が集会の時間です。その時間に、絵本を読んで、歌を歌って、担任の話を聞いたりして過ごします。そんな生活の中で、自分で決める時間が大切な時間と考えています。この後の長い人生を生きていくうえで大事な資質になると思います。そのことは大人が決める生活の中では育ちません。自分で決める経験を積み重ねていくしかないのです。けれども、子どもたちは判断をたびたび間違えます。それはまだ経験が少ないのですから仕方のないことです。
間違いながら間違ったことを理解して、正しい判断を身につけていきます。その時に「いいよ、いいよ」「大丈夫だよ」「それでいいよ」と行ってあげれるかどうかです。ところが大人はそんな時にも”がんばれ・がんばれ”といいます。がんばれという言葉が大好きなようです。
自己肯定という言葉があります。人が幸せに生きていくためには絶対必要な価値観です。がんばれという言葉は自己肯定とは全く逆の言葉です。「今のままではだめですよ」「もっと上に行きなさい」という言葉です。幼児期にがんばれの言葉はいりません。子どもたちは「今のままではいけない」「自分のままではいけない」と感じながら成長していきます。それでは安心感には繋がりません。がんばれとは言わないように心がけてください。
幼児期は人間の根っこを作る時期だとほとんどの人が言います。根っことは「価値観」「感性」そして「自己肯定」です。
”安穏”という言葉は幼児教育の中でもすごい言葉です。安心して穏やかにを、いつも思いながら保育を楽しみましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「安穏」 若草幼稚園 理事長 流水龍也
浄土真宗本願寺派 保育連盟発行
「まことの保育」2015年11月号より
日本の子どもたちはいつも、必要以上に興奮状態にあるように感じています。
元気な子どもがいい、元気な声がいい、大きな声で挨拶しましょう、子どもは風の子など、子どものテンションを上げようとする場面が多くみられます。子どももそうでないといけないと思ってしまい、元気な子どももも、テンションの高い子どもを演じているように見えます。大人も子どもは大きな声で話すもので、穏やかにそこにいることはできないと思っているようです。
子どもは安心できると穏やかになります。ところが、ここ何十年かの子どもたちを取り巻く環境は、子どもたちに緊張を強いて安心できる状況ではないように感じます。
子どもが安心できるのは、自分が自分のままで、あるがままにその場所にいられるかどうかです。園が子どもを自分のままでいられる場所かどうかを考える必要があると思います。
子どもはいつも周りにいる大人の顔色を見ながら生きています。まず、そのことをしっかりわかってあげないといけません。子どもは小さいのです。子どもの身長は大人の半分くらいいかありません。ということは、もし大人が子どもなら、大人は3m近い大巨人です。それは怖いです。そのことを理解して、子どもに、顔色を見なくても大丈夫だよということをどう伝えていくかということです。
本園は自分のすることは自分が決めることを大切にしている幼稚園です。子どもたちは毎日ほとんどの時間を自分のしたい遊びを見つけて過ごしています。弁当の時間と、帰る前の30分が集会の時間です。その時間に、絵本を読んで、歌を歌って、担任の話を聞いたりして過ごします。そんな生活の中で、自分で決める時間が大切な時間と考えています。この後の長い人生を生きていくうえで大事な資質になると思います。そのことは大人が決める生活の中では育ちません。自分で決める経験を積み重ねていくしかないのです。けれども、子どもたちは判断をたびたび間違えます。それはまだ経験が少ないのですから仕方のないことです。
間違いながら間違ったことを理解して、正しい判断を身につけていきます。その時に「いいよ、いいよ」「大丈夫だよ」「それでいいよ」と行ってあげれるかどうかです。ところが大人はそんな時にも”がんばれ・がんばれ”といいます。がんばれという言葉が大好きなようです。
自己肯定という言葉があります。人が幸せに生きていくためには絶対必要な価値観です。がんばれという言葉は自己肯定とは全く逆の言葉です。「今のままではだめですよ」「もっと上に行きなさい」という言葉です。幼児期にがんばれの言葉はいりません。子どもたちは「今のままではいけない」「自分のままではいけない」と感じながら成長していきます。それでは安心感には繋がりません。がんばれとは言わないように心がけてください。
幼児期は人間の根っこを作る時期だとほとんどの人が言います。根っことは「価値観」「感性」そして「自己肯定」です。
”安穏”という言葉は幼児教育の中でもすごい言葉です。安心して穏やかにを、いつも思いながら保育を楽しみましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「安穏」 若草幼稚園 理事長 流水龍也
浄土真宗本願寺派 保育連盟発行
「まことの保育」2015年11月号より
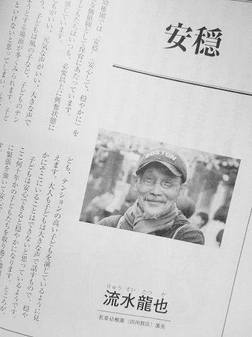
 RSSフィード
RSSフィード